2019年06月29日
奄美民謡について
最近、奄美民謡にはまっていますといっても、沖縄の民謡と半々くらいで練習しているのですが
奄美民謡とは主に奄美群島に伝わっている民謡のことですが、沖縄と混同している人も多いので、地図で確認します

沖縄本島の真上、○で囲まれた地域です
奄美群島で使用される三線(当地では三味線と呼ばれることが多い)は沖縄のそれと同じです
やや大きいと説明されることもありますが、私が現地の製造所やショップで見た限りでは同じでした
決定的に違うのはこれ
絃とバチです
絃は黄色くてとても細いです
黄色いのは昔、卵黄を塗って音に艶を出した名残なんだとか
細いのは音を高くするためです
バチは竹の皮を薄く剥いで加工されています
早いテンポの曲が多いことと返しを多用するためだと思われます
もちろん材料を手に入れやすいこともあるでしょう
胴の皮も強く張り、絃の細さと相まって非常に高音です
私の使用している教則本ではGCGが基本です
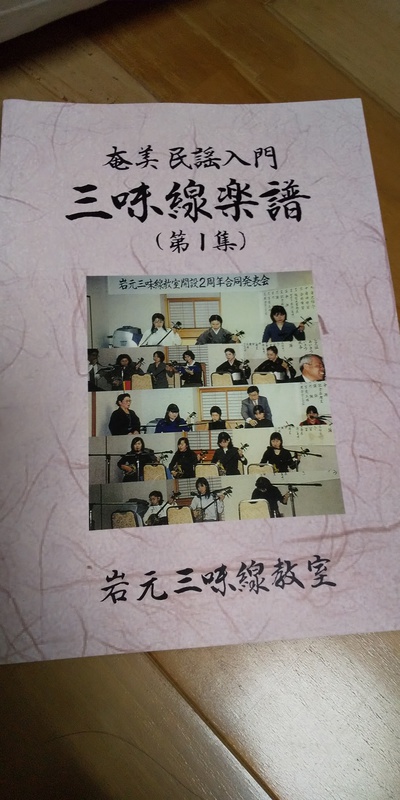
沖縄三線ではCFCを標準とすることが多いようで、それと比べると非常に高いことがわかります
その理由としてよく聞くのが、奄美は女性の神様で、それに捧げる神歌を歌うのがノロやユタというシャーマンだから、うんぬん
というものです
しかし、ノロやユタというのは沖縄にもある、というより沖縄から伝わってきた習俗で、奄美のみ高音域を多用することの理由付けにはなっていないような気もするのですが
奄美民謡を練習し始めて一番驚いたことがあります
沖縄三線を習ったことのある人なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか
薬指を使ってはいけないと
しかし、奄美三線ではなんと!
中指を使わないのです
なんということでしょう
しかも津軽三味線では小指を使わないと聞きました
私は「石の猫」のお話を思い出しました
簡単に言うと迷信がいかにして生まれるかを分かりやすく説明したお話です
http://switchdec.com/stone-cat-1673.html
今回奄美三線を練習し始めて、何となくわかったような気がします
中指と薬指は連動しやすく、混同することが多いのです
もちろんそんなのは初心者ぐらいでしょうが
つまり、「薬指を使ってはいけない」という戒めは、もともとは指使いに不慣れな初心者に対するものであったのではないでしょうか
それが時がたつにつれ本来の趣旨は忘れ去られ、まるで金科玉条の如く妄信的に守られることになっていったのかもしれません
以上の推論は初心者である私の経験から来る思いつきですのであまり気にしないで下さい
絃が三本なのだから指も三本で十分だという考えもあります
しかし、三本より四本で弾く方が演奏の幅が広がることは、合理的にみて当然でしょう
先ほど奄美群島のお話をしましたが、実は沖永良部島と徳之島の間で明確に線引きされるそうです
つまり、沖永良部島と与論島は奄美群島に入りますが、音階は琉球音階に属するみたいです
沖縄に近いぶん影響が大きく残っているのでしょうね
今では島歌と言えば一般的に沖縄地方の歌を指すようになりましたが、もともとは奄美地方の各集落をシマと呼び、その集落に伝わる歌をシマ歌と呼んでいたみたいですね
沖縄で島歌という言葉が使われ出したのはTHE BOOMの「島歌」が大ヒットした後かららしいです
同じ名前の民謡でも各集落ごとにかなり違います
これは沖縄でもよくある話です
しかし、私はそれでとても苦労しています
もともと楽譜がとても少ないのに、それに合う音源がありません
気に入った音源を手に入れても楽譜が合いません
ちなみに奄美民謡は工工四ではありません
また奄美の三線はとてもテクニカルです
難しい小技のオンパレードです
唄はグインという独特のコブシを使って裏声を多用します
裏声は逃げの声と言って嫌う人達もいるみたいですが、世界の民謡で裏声を使うのは奄美民謡とスイスのヨーデルだけらしいです
出ない音域を広げて表現に幅を持たせるのは立派な芸術であり、文化といえます
私はとても魅力を感じます
ただあまり上手でない人が歌うととても音痴に聞こえますがね
色々と勝手な私見を述べてきましたが、沖縄、奄美、どちらも素敵な音楽です
興味とやる気の続く限りどちらも続けていこうと思います
Posted by 三線男 at 00:30│Comments(2)
この記事へのコメント
徳之島には御前風とか全島口説とか十番口説とか継親口説や前原口説みたいな琉球型の口説ものや普通は餅貰いの歌はドンドン節系だと思われがちですが我が故郷徳之島伊仙町や天城町それに徳之島町の北半分の旧東天城村地域では結構な数の集落でドンドン節ではなく沖縄の唐船どーいの曲で餅貰いが行われていますよ。亀津中心の文化圏は奄美式の色が強いんですが、平土野を中心とした伊仙・天城文化圏は琉球色がかなり強いです。沖縄と奄美文化圏の境目は徳之島と沖永良部の間ではなく両島を挟んで北と南の方がまだ近い気がします。ただし、沖縄の飲料水ベンダー会社の営業の北限が徳之島だったり、泡盛などの沖縄の酒類の販売の営業北限が沖永良部島だったり徳之島なら鹿児島側も奄美の地域のも沖縄のものも新聞が通常の契約で配達により読めたりと色々なものの境目が曖昧に存在している地域なのは間違いないですね。
Posted by 闘牛男 at 2019年09月28日 16:30
初めまして、闘牛男さん(^^)/
コメントありがとうございます
返信が遅くなりましてすいませんm(__)m
闘牛男さんは徳之島在住なのでしょうか?
民謡や民俗学にもお詳しいようで、専門的過ぎて奄美群島初心者の私には理解出来ないものもありますが、餅貰いの歌は坪山豊さんの歌を何度か聞いたことがあります
良い歌なのでいずれ覚えたいと思っていますが、シマ(集落)によってまた随分違うんでしょうね、楽譜もないし(T_T)
琉球音階と律音階(日本音階)の境界の話ですが、私のは奄美博物館の受け売りですので、初心者向けに分かりやすくしていたのでしょうね
確かにおっしゃる通り、文化に明確な線引きをするのは難しいと思いますし、複雑に入りくんでいて当然ですね
ところで闘牛男さんは、そのお名前からして闘牛関係者か強い興味関心をお持ちの方だと推察します
実は私、闘牛にも強い関心を持っていまして、是非生の闘牛を見てみたいと願っています
来年辺り大島・徳之島ホッピングを画策しているので、良い情報がありましたらお教え下さいm(__)m
またこのブログに興味がおありの記事でもございましたらぜひぜひコメント下さい
コメントありがとうございます
返信が遅くなりましてすいませんm(__)m
闘牛男さんは徳之島在住なのでしょうか?
民謡や民俗学にもお詳しいようで、専門的過ぎて奄美群島初心者の私には理解出来ないものもありますが、餅貰いの歌は坪山豊さんの歌を何度か聞いたことがあります
良い歌なのでいずれ覚えたいと思っていますが、シマ(集落)によってまた随分違うんでしょうね、楽譜もないし(T_T)
琉球音階と律音階(日本音階)の境界の話ですが、私のは奄美博物館の受け売りですので、初心者向けに分かりやすくしていたのでしょうね
確かにおっしゃる通り、文化に明確な線引きをするのは難しいと思いますし、複雑に入りくんでいて当然ですね
ところで闘牛男さんは、そのお名前からして闘牛関係者か強い興味関心をお持ちの方だと推察します
実は私、闘牛にも強い関心を持っていまして、是非生の闘牛を見てみたいと願っています
来年辺り大島・徳之島ホッピングを画策しているので、良い情報がありましたらお教え下さいm(__)m
またこのブログに興味がおありの記事でもございましたらぜひぜひコメント下さい
Posted by 三線男 at 2019年09月29日 19:18
at 2019年09月29日 19:18
 at 2019年09月29日 19:18
at 2019年09月29日 19:18



